
新型コロナウイルスによるパンデミックは世界を大混乱に巻き込み、特に日本はパニックと集団ヒステリー状態に陥っていた2020年にはじめてこの映画を観た。ものすごくハッピーな気分になったし、思わず人に勧めたくなってしまう。この気分を分かち合いたくなってしまう映画だ。
主演、監督、脚本、プロデュースをひとりでこなしているジョン・ファブローは俳優としても優秀なのだが、監督としてもアベンジャーズとアイアンマンシリーズ、そしてマニアからも評価が高いスターウォーズのスピンオフシリーズであるマンダロリアン、ボバ・フェット、アソーカをプロデュースしている。
この「CHEF」はアイアンマンやスターウォーズのようなSFではなく、ひとりの料理人が繰り広げる喜劇である。特殊効果もほぼないし、リアルな世界でリアルな撮影と編集がされている。あらすじは、マイアミ生まれの主人公カールはL.Aにある人気レストランの料理長をしているが、ある晩、絶大な影響力を誇るブロガー、ラムジー・ミシェルが食べに来た。
気合いを入れて新作料理を出そうと買い出しをして試作をするカール。
しかし、お店のオーナー(ダスティン・ホフマン)に定番料理を出せ、逆らうなここは俺の店だ!と言われ仕方なく従う。ところが、ブロガーから酷評されてしまう。ショックを受けたカールは、10歳の息子パーシーから教わりながらtwitterのアカウントを作り、ブロガーに喧嘩腰のリプを返してしまう。俺の新作を食べにこい!と挑戦状を叩きつけその夜を迎えるが再びオーナーから定番を出せと言われ、逆らったカールは解雇されてしまった。
そして頭に血が昇っていたカールはお店に来ていたブロガーに腹の底に溜まっていた不満をぶちまけて醜態をさらしてしまうのだが、それを周囲のお客さんが動画撮影をしてSNSにばら撒かれ炎上してしまったことで、再就職もできなくなった。
貯金もなくアパート暮らしのカールは途方に暮れていたが、元奥さん(使用人を何人もかかえた豪邸に住んでいる)の計らいで息子の子守役として故郷のマイアミへ行く。元奥さんの最初の夫(ロバート・ダウニー・jr)から88年式のフードトラックを譲り受け、それを息子と、元同僚のマーティンと一緒に改装して絶品キューバサンドを作り上げて、旅をしながらL.Aに戻っていく・・そんな内容だ。
ひたすらご機嫌な音楽が流れるなか、ひたすら美味そうな料理が登場する。
父親カールが息子パーシーに作った朝ごはんのチーズサンド、恋人(スカーレット・ヨハンソン)に作ったパスタ、市場で食べたホットドッグ、そしてキューバサンド。この映画の影響で日本でもキューバサンド(クバーノ)の店が増えたらしい。
カールを取り巻く登場人物もみんな魅力的だ。副料理長を任されながらカールのフードトラックを手伝うためにお店を辞めてわざわざフロリダまでやってきたマーティン(ジョン・レグイザモ)など、最高にクールで人情に厚くてかっこいい。寅さんのような古き良き人情喜劇は、何事にもお金が先にきてしまう現代社会でも大いに魅力的だ。
マーティン役のジョン・レグイザモはアメリカの俳優、コメディアンなのだが、カール役のジョン・ファブローよりも6つ年上と知って驚いた。撮影時は55歳だったらしいが、てっきり35歳くらいだと思っていた。
もう10回以上はリピートして観ている。なんか疲れたなあ、元氣になりたいなあと思った時に観ると、よし明日からハツラツと生きよう!って気持ちになる。劇的な感動を得てアドレナリン分泌させて一時的な高揚感を得ているわけでなく、映画から伝わってくるエネルギーがじわっとひとつひとつに染み込んでいくようなセロトニン的な感覚だ。
主人公カールは、料理の腕前はスペシャルだが思ったことを口に出さないと気が済まない性格で、自分の意見を通すためにストレートに相手に伝えてしまう。素直で嘘がない正直者という見方の方が正しい。そんな性格なので器用に立ち振る舞うことが苦手だ。それは仕事場でもそうだし元奥さんや子供との関係においても同様だ。だから魅力があるのだ。
僕たちは、ついつい自分にも人にも嘘をついて生きている。空気を読んだり、バランスをとろうとするあまり自分の本音がわからなくなってしまっている。だからCHEFを観ていて気持ちいいのは主人公カールが本音で生きているからだろう。社会では生きづらいだろうが、仕事である料理を好きだと公言して、仕事でも私生活でも料理を中心に生きている。
一生懸命に仕事をしている姿が素晴らしいし、羨ましくもある。
僕が惹かれる映画や物語は、登場人物たちがとにかく夢中で仕事をしているものが多い。
アメリカ映画は日本映画よりも親子関係をテーマにしているものが多くCHEFもそうだ。カールは料理人でもあるが父親としても奮闘している様子が描かれている。子供のパーシーは、10歳ながらtwitter、Vine(6秒動画アプリ・現在は終了)、YouTube等を日常で使っている今時の子供で、離婚して別居している父親カールと遊ぶことを求めている。母親との関係もうまくいっているが、父親のことが好きらしい。
父親が作る料理とその腕前を尊敬している様子だし、父親の不器用さも許容している。
父親と同じように素直であるし、母親の賢さも備えた出来た子供がパーシーだ。その対比としてカールの不器用さが余計に強調される。しかし、起用とか不器用とかの評価は幸福には結びつくことが薄いと思う。目の前にある食材をクリエイティブに調理して、出来上がった料理を喜んで食べてくれる人がいる。自分の感覚を信じて、新しいチャレンジをする。失敗したら素直に悔しがって、上手くいったら仲間と酒を飲みながらお祝いをする。
そんなシンプルな生き方をしているカールは本当に幸福なんだと思う。
2014年というSNS成長期ならではの希望があった時代
CHEFは2014年の映画である。この映画ではtwitterが効果的に使われている。僕も2009年にiPhone3GSを買ってすぐtwitterを使い始めた。140文字という制限とまったく知らない人と繋がる面白さに魅了されハマったし、2011年3月11日の東日本大震災では、メルトダウンと放射能などテレビや新聞では知り得ない情報をいち早く手にいれることができ。
そして、何気ないつぶやきに価値があった時代だ。
現在は、役に立たない情報に価値がないとされているが、人目を気にしたりマーケティング(宣伝・広告)が前提の情報は個人的には無価値である。広告に飲み込まれてしまっている経済至上主義な世界のツールに成り下がってしまったのが今のSNSだ。さらに、政府機関による検閲まで入り情報統制がかかるSNSはいわゆるオワコンになってしまった。
毎日雪崩のように溢れている動画コンテンツも同様に価値がほぼなくなっている。
古き良きSNSを描いているこの映画は、例えば10年後、20年後の僕たちが観た時にどのように感じ、思うのか楽しみでもある。息子パーシーのつぶやきで人々がフードトラックに集まり、カールの料理を食べて笑顔になる。実体験をするためのツールという立ち位置こそがSNSの価値であると思うし、デバイスのなかで完結しては人生がもったいない。
iPhoneもSNSもAIも、リアルな体験をして感動を味わうためのツールとして使うことが豊かに生きるコツだと思うし、この映画は少しの勇気を持って前に進むためのエネルギーを人々に与えるのだ。

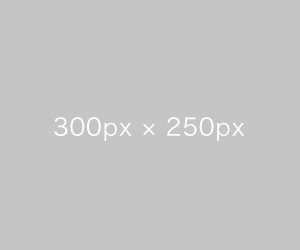
コメント