
大東亜戦争が終わってまだ13年しか経っていない昭和33年(1958)に「彼岸花」が公開された。
日本を代表する映画監督、小津安二郎が親子のしがらみと悲哀を描いた物語で、ものすごく良かった。僕が住んでいる高麗には500万本の曼珠沙華が咲く巾着田という公園があって、猛暑の影響で年々咲くのが遅れている。今年は9月24日くらいから近所の道路が混み出した。駅にも驚くほど多くの人が降りる。
セブンイレブンもうどん屋も阿里山カフェも蕎麦屋も、どこも観光客がいっぱいでうんざりしてしまう。ふだんはポツポツとしかいない人が、まるで銀座や浅草のように溢れかえるそんなこの時期の休みは、煎餅を買い込んで家に籠るに限る。
ということで、無性に小津映画を観たくなってAmazon primeで何本か鑑賞した。


その中で、赤い花が咲き乱れる季節だからなのか「彼岸花」がとても面白かった。当然だが、他の作品もすごく面白い。この時の、僕の氣分に彼岸花の内容が響いた。
親に相談せずに結婚を前提とした交際をしている娘と、結婚に大反対する頑固な父親とのやりとりを中心に、その周囲の人たちを巻き込んで話は展開していく。彼岸花、秋日和(小津の映画)は登場人物が同じで、熟年おやじ4人組と嫁入り前の娘たちをテーマにした家族ストーリーだ。
父親たちは、会社の重役や大学教授で責任がある仕事に就き、マイホームと家族を持った庶民にとっては理想的な暮らしをしている。仕事帰りには、行きつけの料理屋やBARでお酒を飲みながら家族の話題で盛り上がり、家に帰れば家族と向き合って話をする。
この映画が撮影された昭和32-33年という時期は、戦後復興と呼ばれていて、度重なる米軍の空爆によって焼け野原になった東京から、驚くほどの速さで都市が復元されていることに驚かされる。映画で描かれている人々の暮らしは、富裕層ではあるが穏やかで豊かな生活が目を見張る。21世紀になった今現在の日本人よりも豊かな暮らしをしているのだはないかとも思えるほどだ。

あくまで東京という都市部が舞台だから華やかな部分が強調されてはいる。実際に、東京から離れた田舎で育った昭和生まれの僕からすると登場人物たちは眩しいくらいに優雅な生活をしている。
まずは、日本家屋の建築としての様式が素晴らしい。小津安二郎監督ならではの視点と描き方で、その美しさはさらに際立つ。登場人物たちのファッションもまた上品で、特に女性の和服と仕事着がお洒落の極みであるし、話す言葉、話し方も品があって奥ゆかしい。「お洒落」という基準で、現代と比較をしてしまうとこの時代のほうが圧倒的にオシャレだ。
繁華街の看板も、道路を走っているバスも電車もタクシーまでもセンスがいい。

それは単なる懐古趣味ではなくて、昭和から平成に、そして令和になって迷走をつづける僕たち日本人をそのままデザインで表しているのではないかと思ってしまう。それくらい、小津安二郎の映画は美しく精神的に作られている。
そして、キャラクターの個性と俳優さんたちの演技も素晴らしいし、ストーリーと脚本も丁寧に練り込まれている。娘が相談もなく結婚相手と付き合っていることに腹を立てている父親(佐分利信)。父親と家族を暖かく見守る母親(田中絹代)、頑固親父の反対を押し切って結婚をしていく長女の節子(有馬稲子)を中心に物語は進んでいく。父親はシリアスで封建的、でもどこか子供っぽいところも残す性格。母親はこれぞ日本の母、と言った感じの穏やかだけど芯が強く愛情深い。

僕的に好きなのが、父親が京都祇園で馴染みにしている旅館の女将さんと娘の幸子。怒りっぽく厳しい父親のピリッとした空気感が、この二人によってユーモラスで賑やかになり、観ている人々の心を和ませてくれる。特に、昭和を代表する女優のひとり山本富士子さんの美しさと流暢な京都弁は、この映画に華を添えるだけでなく強烈な印象を与えてくれている。
それと同時に、現代の日本という国が時間の経過とともに、じわじわと均一化されていることにも気づかせてくれる。それはテレビの普及と、現在ならスマホとインターネットの影響が大きい。言葉も音楽も、考え方まで平均値が良しになっている。その意味で、言葉についてはまだ関西弁や博多弁、東北弁などがまだ残っていることに嬉しく思う。ただ、山本富士子さんが演じる幸子さんが話すような京都弁はテレビや映画でもなかなか聞くことができなくなってしまったのも事実。地方の言葉も、和服も、たしかに不便ではある。機能的な服が好まれ、コストという考え方が幅を利かせているこの時代だから廃れていくのも分かるが、やはり寂しく感じてしまう。

時代の流れで、暮らしと文化の質が変わるのは仕方がないとは思う。山田洋次監督が寅さんを映画いた26年間でさえ、最初と終わりでは大きく違う。服も街も言葉使いも。ましてや、この映画は68年も昔に撮られたわけだから当時の人が2025年に時間旅行をしてきたら異国に来たように感じるだろう。
果たして、当時の人が現在の日本に滞在をしたとしたら、居心地がいいだろうか?
戦後の復興から高度経済成長を経て、バブル経済に浮かれ、リーマンショックからのパンデミック..そして物価高騰。僕たちの国は、この辺りでしっかりと一度立ち止まって、本当の幸福とか豊かさを真面目に考えた方がいいのではないかと思うこの頃だ。
そんな時があったら、どうか小津安二郎監督の作品を観て欲しいと思う。

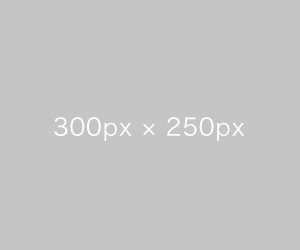
コメント